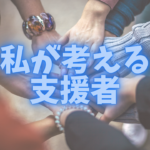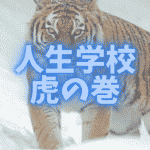「いきなり何の話題ですか?」と思われたかもしれません。
「中学生の自宅学習法」というのは、本のタイトルなんです。
(内藤 勝之:著)
私が、この本と出合ったのは中学生の頃でした。
家にある本で、一番古いかもしれません。
私は結構、読み終わったら古本屋に売ってしまうのですが、
この本は思い入れがあったためか手放せず、いまだに手元にあります。
今日はこの、知られざる名著について書いてみたいと思います。
PR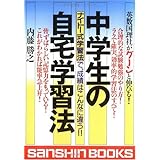 |
|
中学生の自宅学習法―ナイトー式学習法で、成績はこんなに違う!! (産心ブックス) 中古価格 |
![]()
皆、素晴らしい記憶力を持っている
本書ではプロローグとして、
当時人気があった(今でも?)テレビゲームを引き合いに出して、
「皆、素晴らしい記憶力を持っている」ということについて書かれています。
ドラクエⅣというゲームがあるのですが、
このゲームをクリアするために覚えなければいけない事項は、
- 呪文に関する事項 232個
- 武器 19種
- 防具 17種
- モンスター 43種
といった具合で、合計351個でした。
一方、著者のお子様(中1)の期末テスト範囲で覚える事項は、
- 英単語 43個
- 植物名 41個
- 地名 68個
- 物品・産物名など 70個
といった具合で、合計330個だったそうです。
では、みんなゲームの事項は簡単に覚えてしまうのに、
テストでは苦労するのはなぜでしょうか?
どうやら、勉強が「できる」「できない」は、
「記憶力」や「頭の良し悪し」ではなかったようです。

小学校を一年半で卒業
続いて、著者の経験のエピソードが語られます。
著者は病気のため、小学1年以降、学校に通えなくなり、
(いわば、不登校やひきこもりのような状態だったと思われます)
やっと学校に通えるようになったのは、小学6年の年齢の秋頃だったそうです。
一応枕元には小二から小六までの姉の古い教科書を置いていましたが、何ひとつ勉強していませんでした。ですから、たった一~二ヵ月で四年あまりの分の教科書を勉強するのは不可能ですし、年齢通り六年生に編入してもらうように頼むというのは、とうてい無理な状態でした。
中学生の自宅学習法
やっと病気が回復して、学校に通える状態になったのに、
勉強の遅れから、年齢通り6年生には編入させてもらえそうにないという状況。
それでも学年が遅れるのは絶対嫌だと思っていた著者に、
著者の父はアドバイスします。
しかしこの時、私の父は小学校で習うことはそんなに難しくないから、基本のみを確実に覚えておいたら後は何とかなると考えたのです。(この時、父はこの考えにどれぐらい確信があったのか、いつか聞こうと思いながらその機会をうしなって、結局、父の生きている間に聞けずじまいだったことを今では残念に思っています)父は、どうしても知っていなければ困ると思われることだけ、急いで教えてくれました。
中学生の自宅学習法
それは、次の4点でした。
- 算数の九九
- 整数と分数の四則計算
- ローマ字
- 漢字の書き方
この4点だけは確実に習得し、
そして「療養中ずっと勉強していたから」と小学校の校長先生に交渉して、
なんとか、秋から6年生として迎えてもらうことができたそうです。
療養中、実際は勉強らしいことは何ひとつしていなかったのですから、学校へ通い出したら皆についていくのは相当大変だろうと覚悟していました。ところが意外なことに、実際にはほとんど何も困らなかったのです。
中学生の自宅学習法
もっとも、上記の4点しか勉強していないのだから、
皆についていくのは相当大変だろうと覚悟していました。
しかし意外にも、ほとんど困ることはなかった。
この経験から、勉強というのは基本が大切なんだということを実感したそうです。

著者の自宅学習法
著者の提唱する勉強法は基本重視。
基礎の部分が不十分なまま、
その先の、枝葉末節のことを覚えようとしても上手くいかないと言います。
「1冊完全主義」という方法が象徴的です。
それは、一度に沢山の教材に手を出すのではなく、
テキストを1冊、それも出来るだけ薄いものに絞り、
そのかわり、それを何度も繰り返してマスターするというものです。
ひとつの教材を確実にマスターするという方法が、最も楽なやり方で、かつ成果が最大となります。そして、その教材を完全にマスターしたら、次の教材に移ればよいのです。その場合は、最初マスターした教材に欠けていたことだけを追加すればよいのですから、非常に効率的です。
中学生の自宅学習法
本書では他にも、
「唱えながら書く」「コンパクトなまとめを作る」などの様々な工夫や、
各教科、学年に応じた勉強方法、
著者の教育論に至るまで、深く掘り下げて書かれています。
また、この自宅学習法を武器に、
ハンデからのブランク、遅れを取り戻し、
名門大学に合格し、博士課程に進学し、
やがてナイトー塾というのを開かれるのですが、
そんな著者のサクセスストーリーを、当時ワクワクしながら読んだものでした。

大きな影響を与えてくれた1冊
本書の最後に著者の恩師が登場し、
著者の思い出やエピソードが語られます。
つまり、著者は既に亡くなっていたのです。
当時、衝撃を受けるとともに、
人は何のために学ぶのだろう、人生とは何だろうと考えされられました。
本書は自宅学習法のタイトルの通り、
病気のため、ひきこもりや不登校のような状況に追い込まれた著者が、
ハンデを克服するために創意工夫した、
自宅で一人で学ぶための学習法が紹介されています。
その方法や考え方は、子供から大人まで参考になると思います。
私のその後の人生に、大きな影響を与えてくれた1冊でした。
その時どのようにして学校で仲間に追いついたかは本文中で語っているので、読まれた方はおわかりでしょうが、その時の克己心が今度の二度目の病の時にも発揮された。彼の科学者精神が生かされたのは、実はここからだった。治療するのは医師であるが、彼はその治療法を検証しながら治療を受けるといった姿勢で臨み、医師も驚くほどの効果を上げてきた。
中学生の自宅学習法
彼のこれまでの人生は辛い時があったにもかかわらず、いつも自信をもって乗り切っている。これが内藤流のやり方だというように・・・・。
長い闘病生活を経たのち、平成五年三月、不幸にして内藤君は永眠されたが、今でも多くの生徒たちがナイトー塾で学び、ナイトー式勉強法を体得している。
中学生の自宅学習法